|
|
| ニューヨーク 1923年 |
1923年10月、パウル・フェヨスは、ニューヨークにレバイアサン号でたどり着きます。
1910年から1920年にかけて、ヨーロッパから多くの移民がアメリカに流入しています。多くの芸術家や科学者などもいますが、だいたい親戚を頼ってくる場合がほとんどです。しかし、パウルは全くの天涯孤独でした。誰も知らない。英語も話せない。アメリカのこと自体良く知らない(母親は、ニューヨークの外に出ると、インディアンに食われるから出ないでくれと懇願したそうです)。なぜか、パウルは自分は重要人物だからとニューヨークきっての高級ホテル、ウォルドーフ・アストリアに泊まっていたのですが、すぐに所持金は底をつき、自分の持ち物を質屋に入れようとして馬鹿にされる始末。安宿に移ったものの、仕事が見つからない。正確に言うと、どうやって仕事を見つけたらいいかわからなかったのです。毎朝、朝7時半にきっちり起きて、ニューヨークの街中を歩いて、帰ってくる。そんなことをしても、仕事など見つかる訳ないのですが。
ある日、疲れてしまったのでベンチで休んでいると、隣にみすぼらしい身なりをした男が座って話しかけてきました。英語がわからないパウルは、それでも「cigarette」だけはわかったので、彼にタバコをあげました。ほとんど会話はできなかったのですが、男は陽気に話しかけてきます。「ドイツ人か」とか、「いい天気だな」とか。パウルは不思議に思いました。アメリカ人は全員働くと聞いている、なのにこの男は昼の11時に何もせずにいる、どういうことだろう?つたない英語で聞くと、彼は午前中働いていたが、クビになったと言うのです。
「働いた分だけは手当てをもらったんでね、今日はもういいんだ。明日もまた働けるさ。」
明日、どうやって仕事を見つけるの?
「真夜中に街に出て行って、ニューヨーク・ワールド紙を買えばいい。そうして求人欄をみて、『腕っぷしのつよいヤツ求む』以外で、気に入った求人を見つけるのさ。朝一番にその住所に行けばいい。昨日は、俺は溶接工だったんだよ。溶接のことなんて、何も知りやしない。朝の8時に雇われて、10時半にクビになった。でも働いた分はもらえるんでね。」
これは夢の国だ。
パウルはその夜、早速ニューヨーク・ワールド紙を買い、次の朝、ニューヨークのウィンターガーデン劇場の通用口で、列の先頭で待っていました。それから2週間、彼はウィンターガーデン劇場の舞台の仕掛けの「太陽」の役をやります。円形の反射板をアスベストの手袋で持って、舞台の背景の後ろに立っているだけです。劇場は2週間で御用済みになり、その次は、葬儀屋。喪服を着て、参列者に「足元にお気をつけください」とだけ言うのですが、Watch Your Stepsの”W”がどうしても発音できない。それからピアノ工場。ここは自動演奏ピアノの工場ですが、最初は運搬、そして組立工程。週18ドル。
ようやく、食べていけるだけの収入が手に入るようになったパウル・フェヨスですが、遊ぶ金はありません。彼は「無料」で楽しく過ごすことを覚えます。その頃のニューヨークにはいろんな享楽があり、ぶらぶら見ているだけで十分面白いものもあったのです。彼は10セントストアに入り浸り、そこで庶民、というより資本社会の底辺の人たちの娯楽を吸収していきます。おそらく、このときの記憶が、「都会の哀愁」や「君と暮らせば」などの映画作品にずっと残っているのではないかと思います。
|
|
| ウィンター・ガーデン劇場 1923年 |
ある日、彼は通りで「化学者クラブ」という看板を見つけます。「無料講演会」とあって、英語の勉強になるかと思って聴講するのですが、さっぱりわからない。隣は「化学者クラブ職業斡旋所」となっているので、早速入ってみると、若い女性がめんどくさそうに応対する。
「で、何?」
「仕事が欲しいんです。」
「あんた、化学者?」
「いいえ、医者です。検査ラボとかで使ってもらえないかと」(ちなみに彼は医者であることをこのときまで誰にもずっと言っていません。)
「この書類に書いて」
パウルがすっかり書き終えると、
「じゃ、5ドル」
お金が必要だったとは、このときまで知らなかったパウルは動転します。ここにきて相手の女性が大騒ぎ。
「え、何、お金ないの、何、いい加減にしてよ、この書類、通し番号振ってあんのよ、どうしてくれるのよ!」
「お金を払わないといっていません、後でもってきます。」
「冗談じゃないわよ、そうやって逃げるつもりでしょ、泥棒!」
騒ぎを聞きつけたマネージャーが現れ、パウルの申請書を見ます。
「君は医者なの?」
「そうです。」
「卒業証書(ディプロマ)は持っているかい?」
「ええ、家に。でもラテン語ですよ。」
「ああ、いいよ。持ってきてくれるかな?で、今何してるの?」
「ピアノ工場の日雇いです。」
2日後、ロックフェラー研究所からパウル・フェヨス宛に電報が届きます。水曜日の10時、フレクスナー博士のオフィスに来て欲しい、という内容でした。
サイモン・フレクスナー博士は、赤痢菌の研究や脳脊髄膜炎の研究で有名です。野口英世とも共同で研究したことがあります。もうこのときは白髪の老人でした。
「君が、医師で、ピアノ工場で働いているんだね。どうして医師の仕事をしないの?」
「英語ができないからです。」
「ほかにはどんなことができるの?」
「馬に乗れます。」
「どれくらい上手いの?」
「走る馬の鞍の上に立って、電線を切ることができます。」
「君はいったい何者なの?医師?ピアノ工?馬乗り?」
フレクスナー博士は侮辱ではなく、本当に不思議に思ったようです。
次の日から、ブロンフェンブレナー博士の研究室で働くことになりました。朝一番に行くと、ブロンフェンブレナー博士は、
「ここにボツリヌス菌がある。これをネズミに投与して、MLDを出して欲しい。」
と言っていきました。
パウルは、一人で実験室に座ったまま、何時間もフラスコをじっと見つめていました。ボツリヌス菌ってなんだ?MLDってなんだ?どうやってMLDって出すんだ?ああ、やっぱりダメだ。僕は偽者だ。今からブロンフェンブレナー博士のところに行って、告白しよう。私は何も知らない偽者です。クビにしてください。
「何だって?知らないんだったらどうして聞かないんだい?ほら図書室もあるんだよ。ここで調べられるし、わからなかったら聞けばいいんだよ。誰だって最初は何も知らないんだよ。」
ロックフェラー研究所といえば、世界でも有数の学術機関です。そこの博士ともなれば、威張り散らしていてもおかしくないでしょう。○○大学出身だとか、そういったことで人を見下す人は昔も今も変わらずいます。このときのパウル・フェヨスを侮蔑し、研究所から追い出した人がいても全くおかしくありません。しかし、このブロンフェンブレナー博士の言葉と態度こそ、その後のパウル・フェヨスという人物を作ったと思うのです。マダガスカルやアンデスの先住民と接するときにも、彼は謙虚で、「知らない」ということをはっきり言える人でした。自分が「文明人」だからと、見下すことはなかったのです。ブロンフェンブレナー博士のこの言葉に救われて、パウル・フェヨスは「自分の人生でもっとも幸福な年月」をロックフェラー研究所で過ごします。
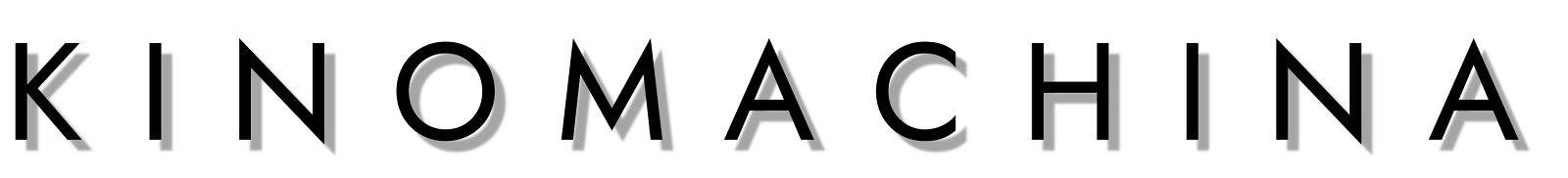

0 Comments
Post a Comment