|
|
|
春の驟雨 撮影セットで 中央 パウル・フェヨス、右から二人目 アナベラ (via filmkultura.hu) |
ヨーロッパに戻ったパウル・フェヨスは、フランスを訪れ、そこで「ファントマ(原題:Fantômas)」を監督します。例の「謎のファントマ」ものです。そして1932年にハンガリーに舞い戻って「春の驟雨(原題:Tavaszi zápor)」を監督します。これは、パウル・フェヨスの最高傑作とする人も多く、私もこの映画がもっとも好きです。若い女性が過ちを犯し、妊娠し、子供を生みますが、子供は取り上げられ、彼女は失意のうちに亡くなります。天国に上った彼女は、自分の娘が大きくなって、同じ過ちを犯そうとしているところを見て、雨を天から降らせて娘を守るというお話です。この映画では、主人公のマリー(アナベラ)が未婚で妊娠したために、村で、そして都会で疎外されていく過程が、実に辛辣に冷酷に描かれています。特に子供を取り上げられて、村に舞い戻り、道端で子供たちにまでさげすまれて、汚れ、朽ち果てた彼女が、世を恨み、神を恨むさまは、この時代の作品には類を見ない強烈な印象を残します。そのため、この映画はハンガリーで「共同体と神を冒涜した」とされて上映禁止になり、ニューヨークでも上映禁止になります。
|
|
| 美術監督 ハインツ・フェンチェルと。 「君と暮らせば」のセットで (via davidkultur.at) |
1933年にはウィーンで「君と暮らせば(原題: Sonnenstrahl)」を監督します。これもシンプルなストーリーで、貧乏のどん底にいる若い二人が様々な苦難を乗り越えていく話です。結婚式の場面は、ムルナウの「サンライズ」そのままですし、随所に影響を見ることができます。私は、フランク・キャプラはこの映画から「素晴らしき哉、人生(1946, 原題:It's a Wonderful Life)」のヒントを得たのではないかと思っています。貧乏に耐えかねた主人公が飛び込み自殺をしようとしているときに、別の人間が飛び込み自殺をして、それを助けてしまうというオープニング。そして、お金に困って、もうどうにもならない、と言うときに、みんなが少しずつ出し合って、窮地から救われるというエンディング。それにしても、パウル・フェヨスは貧乏のどん底で暮らす人々を描くことにかけては、実に真摯で、かつ容赦ありません。表面は砂糖でコーティングしているのですが、その奥底には、実際に経験した人間だからこそ表現できる、冷徹さがあると思います。
パウルは、1934年にコペンハーゲンのノルディスク・フィルムと契約します。ここで、3作品ほど監督するのですが、彼はこの前後から「フィクション」の映画を作り続けることに限界を感じ始めます。何も「新しいこと」が生まれてこない焦燥が日増しに強くなっていました。しかし、彼はヨーロッパでは「一流監督」として認められていて、ノルディスクは彼に様々な ーー興行的にも、芸術的にもーー 期待をかけています。ある日、焦燥の頂点に達したパウルは、ノルディスクの重役会議にひとり乗り込んでいきます。
「私は、もう辞めたい。契約を破棄したい。」
実は契約はまだ2年残っていて、重役たちはそんな申し入れは当然拒否しました。
「拒否するならすればいい。私は病気だ。私は働けない。」
「君の好きにしていいから、映画を作り続けてくれないか。会社はどんなことでもしよう。」
「ここでは、映画は作れない。こんなところでは無理だ。」
「じゃあ、どこなら作れるのだ?パリか。ロンドンか?」
とにかく辞めたい一心で、彼は会議室の壁に貼ってあった世界地図の上で、自分の指の届くところにあったマダガスカルを指差して言ったのです。
「ここでなら。」
パウルは、マダガスカルのことなんかなんにも知りません。そんな島があることさえ。
「どうして、マダガスカル?」
「どうしてって、そこには原住民がいて、私は原住民と仕事をしたい。」
「マダガスカルか、よろしい。カメラマンは誰がいい?」
|
|
| パウル・フェヨスのノルディスク時代の作品 「黄金の笑顔(原題:Det Gyldne Smil)」 |
彼が本当に「原住民と仕事をしたかった」のかどうか、あるいはこの重役会議の話が彼の「脚色」なのかは、定かではありません(この話は後年になって彼自身が口述したものから採られています)。ある側面では、この方向転換はそれほど異様なものではないと思います。1930年代に、とくにヨーロッパでは「文化映画」と呼ばれる、「学術性の高い」ドキュメンタリー映画の製作が盛んになるからです。この「学術性」に括弧がついてしまうのは、啓蒙的な側面が多分に強いのと、これらの映画のかなりの部分がプロパガンダ性の高いものも多かったからです。
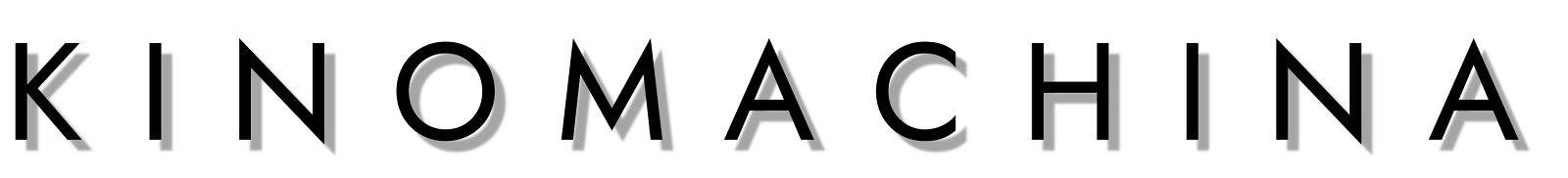

0 Comments
Post a Comment