 |
| 「會議は踊る(Der Kongress danzt, 1931)」の撮影風景(filmprotal.de) この吊ってあるカーボン・アーク灯が落ちて事故になったという記述があります。 |
カメラマンのカール・ホフマン(1885 - 1947)は、10代の頃から映画業界に入って、現像技師、映写技師などを経験し、1916年にデクラ社のカメラマンとなります(1)。そこで彼は、エーリッヒ・ポマーのもと、オットー・リッペルト監督の「ホムンクルス」6部作やアルウィン・ノイシュのメロドラマの撮影を担当します。1920年にフリーランスのカメラマンになり、フリッツ・ラングの「ドクトル・マブゼ(Dr. Mabuse, dir Spieler, 1922)」、「ニーベルンゲン(Die Niebenlungen, 1924)」、F・W・ムルナウの「ファウスト(Faust, 1925)」などの作品に参加します。20年代の末には自ら監督もするようになりました。彼はトーキー導入によってカメラが静止してしまうのを嫌い、「トーキー技術を導入してもカメラは自由に動かせるべきだ」と考えて実践しています。「會議は踊る(Der Kongress danzt, 1931)」は、リリアン・ハーヴェイ主演のヒット作として有名ですが、カメラは実に自由に動き回っています。「麦藁帽子(Der Florentiner Hut, 1938)」は、ウーファの製作責任者だったウォルフガング・リーベンアイナーが監督し、カール・ホフマンが撮影を担当した、当時としては実験的な映画です。まず、導入部にタイトルや出演者・スタッフの字幕が無く、それらはすべて大道芸人が歌っている歌詞のなかで紹介されます。そして、映画の中では「一人称のカメラ(subjective camera, POVショット)」が頻繁に使用されます。これは主役のハインツ・リューマンの視点から見えることを移しているのですが、婚約者や訪問客とキスをするシーンなど生々しいんですね。さらにプロットを推し進めるのに、ハインツ・リューマンが映画の観客に話しかける(第4の壁を破る)のです。
「一人称のカメラ」は、劇映画では時折挿入されることはあっても、ずっと長回しで使われることはあまりありません。有名な例として、ロバート・モンゴメリーが監督(および主演)した「湖中の女(Lady in the Lake, 1947)」で、これは全編「一人称のカメラ」でフィリップ・マーロウの世界を表現しようとしたのですが、実験的すぎたようです。「麦藁帽子」では、ハインツ・リューマンのコメディということもあって、むしろ良い効果を挙げているかもしれません。 カール・ホフマンは戦争末期にアグファカラーの「すばらしい日(Ein toller Tag, 1945)」にも参加しますが、それが最後の仕事となりました。
美術を担当したハンス・ヤコビー(1904 - 1963)は、むしろ脚本家として有名です。1933年にナチスが政権をとったときにはスペインに亡命、そこで内戦が勃発すると、ローマからパリへと向かいます。しかし、ここもナチス・ドイツによって占領されるわけで、逃げる先々にファシストたちがやってきてしまう。なんとかアメリカに亡命してユニバーサルにもぐりこみます。ここで彼は「オペラ座の怪人(Phantom of the Opera, 1943)」そしてターザンシリーズの脚本を共同執筆します。ハンフリー・ボガートのサンタナ・ピクチャーズの「モロッコ慕情(Sirocco, 1951)」も彼の脚本です。50年代にドイツに帰国し、ハインツ・リューマンのヒット作を書きました。
「誘惑」は恐らく全く人口に膾炙することなく忘れ去られてしまったのでしょう。プリントも存在も確認できません。ランプレヒト監督が「第五階級」の直前に撮った作品ですが、その萌芽はこの作品にあったのか、と言う点は気になりますが。
(1)Hans-Michael Bock, Tim Bergfelder ed., "The Concise Cinegraph: Encyclopedia of German Cinema"
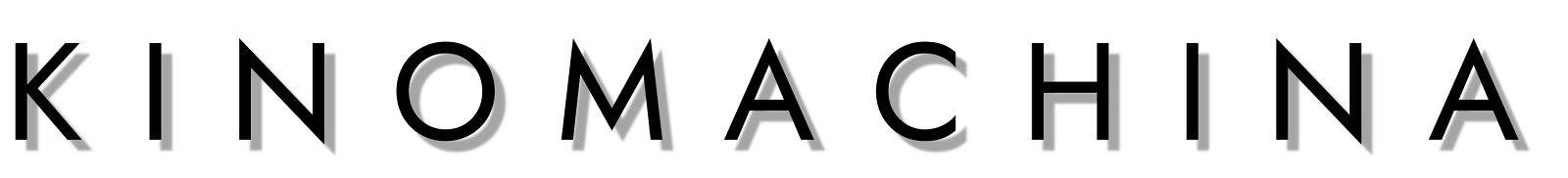

0 Comments
Post a Comment