
|
|
『オズの魔法使(1939)』カンサスパート このパートに施されていたセピア調色をデジタルバージョンで再現 |
セピア調色
無声映画の時代には、上映用プリントを染色(Tinting)したり、調色(Toning)したりすることが一般的に行われていた。染色は、白黒プリントを染料の槽に浸漬して映像に色調を与える方法である。染料がエマルジョンにしみ込んで染色されるため、白い部分が染料の色に染まるが、黒い部分は元の白黒プリントのハロゲン化銀による。つまり、映像の色階調は、染色の色~黒となる。一方で、調色は、ハロゲン化銀を別の発色材料で置き換える方法だ。これは化学的なプロセスで行われる。この方法だと、白い部分は白いまま、黒い部分が調色されるため、映像の色階調は、白~調色の色となる。染色と調色は組み合わされて施されることも多く、かつ、シーンごとに色のスキームを変えるのが一般的だった。
トーキーの登場とともに、染色や調色が敬遠されるようになった。光学サウンドトラックが、染色や調色の影響を受ける、というのが主な理由として挙げられている。だが、徐々に染色も調色も見直されるようになった。特に1930年代後半にMGMが《セピア調色 Sepia Toning》に並々ならぬ力を入れて、いくつかの映画で採用されていたことは注目に値する。
まず、MGMがセピア調色を大々的に宣伝したのは、パール・バックの注目作を原作にした『大地(The Good Earth, 1937)』が最初である。アーヴィング・タルバーグが『大地』をセピア調色で見せることを望んでいたという。MGMの現像部門のトップ、ジョン・M・ニコラウスが技術を検討、1937年の劇場公開用プリントでは全編にわたってセピア調色が施され、話題になった[1][2]。次の『君若き頃(Maytime, 1937)』もセピア調色が採用された。他社も後を追うようにセピア調色を始める。20世紀フォックスの『テンプルの軍使(Wee Willie Winkle, 1937)』[3]、デヴィッド・O・セルズニック製作の『ゼンダ城の虜(The Prisoner of Zenda, 1937)』[4]などもセピア調色プリントで公開されたと当時の業界紙は報じている。さらに『アリババ女の都へ行く(Ali Baba Goes to Town, 1937)』 [5]、『アイス・フォリーズ・オブ・1939(Ice Follies of 1939, 1939)』 [6] や、その他多数の短編映画がセピア調色で公開された。MGMの広報部は、このプロセスに「プラチナ・セピア(Sepia Platinum)」という名前をつけて、高級感を出そうとした。
そして『オズの魔法使(The Wizard of Oz, 1939)』である。これは、3-ストリップ・テクニカラーで公開された作品だが、カンサスを舞台にした導入部と終結部は白黒フィルムで撮影され、この部分はセピア調色が施されて公開された。セピア調色のパートからテクニカラーのパートに変わるところは、実に丁寧に仕上げられていて、今でも話題になる。監督としてヴィクター・フレミングがクレジットされているが、リチャード・ソープ、ジョージ・キューカー、キング・ヴィダーも監督として参加している[7]。導入部のセピア・パートの最も印象的なシーン、ドロシーが「虹の彼方に(Over the Rainbow)」を歌うシーンは、キング・ヴィダーによるものである。
戦前のハリウッドのトーキー映画のなかに、染色や調色されたものがあったというのは、映画ファンのあいだでもあまり知られていない。それは染色や調色が施された公開時のプリントが失われてしまったことや、戦後の再公開やリバイバル上映の際に準備されたプリントが白黒だったことから、そのまま白黒プリントが流通してしまって広まってしまったことが要因だろうと思われる。
また、染色、調色という映画のカラー技術が忘れられてしまった経緯には、1950~60年代のTV放映が果たした役割もあるだろう。『オズの魔法使』がアメリカのTVネットワーク、CBSで初めて放映されたのは1956年だった。この時から、放送自体はすでにカラー放送で行われていたのだが、大半の家庭のTV受像機が白黒だったという。その後もカラーTVが広く浸透する1960年代まで、多くの家庭で『オズの魔法使』は白黒映画だった。そのような状況の中で、TV局側がセピアパートの色を復元することに意義を見出せなかったのは、想像に難くない。『オズの魔法使』は、そのステータスゆえ、特別扱いでカラー放映だった1) が、ほぼすべての映画は白黒放送で行われていたため、『大地』や『テンプルの軍使』のTV放映時に調色をする意味は全くなかった。テレヴィジョン技術の変遷がもたらした思考、すなわち白黒か、カラーかという二分法が、映画の《色》の文化にも大きな影響を及ぼしたのは間違いないだろう。
だが、TVは仕方ないとしても、なぜ劇場での再公開やリバイバル公開まで白黒プリントになってしまったのだろうか。それはセピア調色で使われる材料に理由があった。MGMの広報部は「プラチナ・セピア」と名付けたが、この調色プロセスではプラチナは使われていない2) 。実際に使われていたのはウラン化合物であった。
硝酸ウラニル
MGMの現像・映像部門のトップのジョン・M・ニコラウスは、『大地』の公開に合わせて、《セピア調色》の技法をJSMPE(Journal of the Society of Motion Picture Engineers, 米国映画技術者協会誌)に報告している[8]。《セピア調色》の技法は19世紀末からすでにガラス乾板写真の分野で知られており、映画フィルムの分野ではコダックが「T-9」という処方を1929年に公開していた。ニコラウスによれば、MGMの《セピア調色》はこの処方を利用しているという。
- 硝酸ウラニル 16.5オンス
- シュウ酸カリウム 16.5オンス
- フェリシアン化カリウム 6.5オンス
- アンモニウムミョウバン 2.5オンス
- 塩酸(10%) 10クォート
- 水 残部
- 合計 50ガロン
硝酸ウラニル(uranyl nitrate)は UO2(NO3)2であらわされる化合物である。黄色を呈しているが、これは六価のウランに由来する。《セピア調色》では、この処方に調製した調色槽に現像済みのポジティブ・プリントを浸漬し、化学反応によって、フィルムのハロゲン化銀を硝酸ウラニルに置き換えるのである。念のために書き添えておくが、セピアの色はウランが発する放射線とは関係はない。また、ウランをガラスに微量配合して得られる「ウランガラス」の示す淡い緑色の蛍光も、このセピア調色で使われるものとは違う。あくまでウラン(VI)の色だ。
映画『大地』は全14巻、およそ12,000フィートの長さがあった。ネガからおよそ500本のプリントが作られ、これらすべてに調色を施した。
John M. Nickolaus
これだけの量のプリントを公開前の短いスケジュールで調色しなければならないとなると、調色槽処理や乾燥などはすべて自動化されなければならない。MGMが力を入れたのは、この自動化の過程である。MGMは翌1938年の1月、4台の調色装置を導入したと発表した[9]。これで1時間当たり5,500フィートを調色処理できるようになったという。

|
| MGMに新しく設置された《セピア調色》の設備 Motion Picture Herald January 19, 1938, 130 (5), p. 11 |
つまり『オズの魔法使』のセピアの世界は、広島に投下された原子爆弾の原料3) と同じもので作られている。
『オズの魔法使』公開後も《セピア調色》されたプリントを使った映画は、いくつか公開されているが、以前ほどの勢いはなくなってきていた。1940年代になると、セピア調色された映画は数えるほどしかない。私が長編映画について調査した限りでは、『スワンプ・ウォーター(Swamp Water, 1941)』[10]、『ストーミー・ウェザー(Stormy Weather, 1943)』[11]のみがセピア調色のプリントで公開されたようである。
たしかに『大地』が公開された当初の驚きや人気が、年とともに薄れていったということもあるだろう。だが、《セピア調色》が消えていった本当の理由は別にあったようである。
ダグラス・フェアバンクス・ジュニアの『エグザイル(Exile, 1947)』は「セピアトーン」でプリントが作られるが、これは7年ぶりになる。茶色に調色された映画は、戦争が始まって以来、製作されていないが、それはプロセスの主要成分であるウランが、アメリカの核開発計画によって独占されたからである。まだこの元素は入手できないが、ユニバーサル=インターナショナルのカメラ・現像部のトップをつとめていたジョージ・セイド氏が、実験を通して新しい方法で茶色に調色する方法を編み出した。彼の実験では、ウランの代わりに新しい複数の成分を使っている。セイドによれば「セピアトーン」を使えば白黒映画と同様に、簡単にプリントができるという。
Variety, October 22, 1947
『オズの魔法使』が公開された1939年、人類の大部分はまだウランの重要性に気づいていなかった。ラドンの採掘の際に出る副産物として得られ、窯業で着色に使われるくらいだった。しかし、前年の暮れ、ベルリンでオットー・ハーンとリーゼ・マイトナーらがウランの核分裂を発見しており、エンリコ・フェルミとレオ・シラードらは、これをナチスが利用することを警戒し、警鐘を鳴らした。彼らが危惧した通り、ナチス・ドイツはズデーテン地方を併合した際に、ヤーヒモフで採掘されるウランの売買を禁止した。ベルギー領コンゴのシンコロブエ鉱山のウラン鉱は当時世界最大のものだったが、ナチス・ドイツがベルギーを占領すれば、ここも彼らが掌握することになる。鉱山の所有者だったユニオン・メニエール社は、戦争によって需要が増したコバルトと銅の採掘に力をいれるために、シンコロブエ鉱山を閉山したものの、コンゴとベルギー国内に相当量のストックがあった。そして恐れていた通り、ベルギーを占領したナチスはベルギーオレンの精製工場にあった3500トンを接収した。。ルーズベルト大統領は、1939年10月に「ウラン諮問機関」を設立するが、ウランの入手先は簡単には見つからなかった[12][13]。政府がウランの売買を禁止したのも当然であろう。セピア色のカンザスこそが、虹の向こうに行ってしまった。
アメリカ陸軍が結成した「マンハッタン工兵管区」のグローヴス准将が、ニューヨークのスタテン島の倉庫に1200トンのウラン鉱の在庫があることを知るのは、1942年の9月のことである。この在庫は、この2年前の1940年に、ユニオン・メニエール社のエドガー・サンジエがナチスの手にわたることを避けるためにひそかにコンゴからニューヨークに送らせたものだった。
ジョージ・セイドのセピアトーンは普及しなかった。『オズの魔法使』は、戦後の1949年にアメリカで再公開されているが、この時すでにカンサスパートはセピアではなかったという。その後、前述のTV放送も含めて、セピア調色がよみがえることはなかった4) 。カンサスパートがセピアになるのは、1989年の公開50周年記念の再公開の時である。当時MGMのライブラリの大半を所有していたターナー・エンターテイメントがプリントを準備し、MGM/UAが配給した。新プリントは、すべてカラーストックで、セピアパートもカラーフィルムでセピア調色の効果を出した。オリジナルのように白黒フィルムにウラン化合物を使って調色したわけではない。
それでも、『オズの魔法使』は、そのセピアパートが復活しただけでも幸せだろう。他の映画はセピア調色されていたことさえも忘れ去られてしまっている5) 。私は「セピア調色で公開された映画はセピア調色で見るべきだ」とは言わないが、どんな風に見えるのだろうか、というぼんやりとした疑問を持っている。ウランという元素が広く大衆には知られていない時代の、やや無邪気な色。その後の出来事について知っている私たちには、その無邪気さを感じることは、かなり困難になってしまったかもしれないが、とはいえ、私たちの方が当時の人々と比べて賢いわけではない。むしろ私たちが失ってしまったものを、その無邪気な色はまだ持っているかもしれない。
Notes
1)^ 『オズの魔法使』のTV放映問題をさらに複雑にしているのが、この映画に関してMGMと独占放映契約を結んでいたCBS-TVネットワークと、そのライバルのNBC-TVネットワークの関係である。NBCはカラーTV受像機の市場をほぼ独占していたRCAの傘下にあった。CBSにとってTVのカラー放送は、ライバル会社に利益をもたらすことにほかならない。「どうしてデヴィッド・サーノフ(RCA会長)がカラーTVで作った損失を、俺たちが埋めてやんなきゃならないんだ」と公言してはばからないCBSの幹部もいたようである。このことが遠因となって、1961年にはCBSは『オズの魔法使』を全編白黒で放送している[14]。
2)^ 写真プリントのセピア・トナーで実際にプラチナが使用されていたこともあった[15 p.144]。
3)^ 正確には、ウラン鉱を硝酸で溶かした硝酸ウラニルが、ウラン精製の出発材料となった。
4)^ コダックが1946年に発行した参考便覧には「Kodak Uranium Toner(T-9)」として硝酸ウランを調色材とする処方が掲載されている[16]。この処方には硝酸ウランが「Kodak Uranium Nitrate」と記載され、コダック・ブランドが存在していたことを示唆しているが、実際この時点でコダックが硝酸ウランを販売していたかどうかは不明である。その後、1950年代のコダックの出版物からはウラニウム・トナーの記載は姿を消し、セピアのトナーは「Kodak Sulfide Sepia Toner」「Kodak Sepia Toner」などの名称で記載されるようになる[17]。どれもスルフィド系のトナーでウラン化合物は使用されていない。
5)^ シカゴ・フィルム・ソサエティのウェブサイトには、現存するトーキー映画の調色、染色のプリントについての解説がある。『君とひととき(One Hour With You, 1932)』も、公開時に調色・染色されていたが、そのプリントが現存するようである。
References
[1]^ "Leo May ’Tone’ All Pictures," International Photographer, p. 15, 1937.
[2]^ "M-G-M to Make Wide Use of Tone-Tint Merging," American Cinematographer, vol. 18, no. 9, p. 372, Sep. 1937.
[3]^ "Showmen’s Reviews "Wee Willie Winkle"," Motion Picture Herald, p. 44, Jul. 03, 1937.
[4]^ "Showmen’s Reviews "The Prisoner of Zenda"," Motion Picture Herald, p. 39, Sep. 04, 1937.
[5]^ "Showmen’s Reviews "Ali Baba Goes to Town"," Motion Picture Herald, p. 50, Oct. 23, 1937.
[6]^ "’Ice Follies of 1939’," The National Exhibitor, vol. 17, no. 17, p. 17, Mar. 1939.
[7]^ "AFI|Catalog - The Wizard of Oz." https://catalog.afi.com/Catalog/moviedetails/7892
[8]^ J. M. Nichkolaus, "Toning Positive Film by Machine Methods," Journal of the Society of Motion Picture Engineers, vol. XXIX, no. 1, p. 65, Jul. 1937.
[9]^ "4 Toning Machines in MGM Laboratory," Motion Picture Herald, vol. 130, no. 4, p. 45, Jan. 22, 1938.
[10]^ "Product Digest: Reviews "Swamp Water"," Motion Picture Herald, p. 318, Oct. 18, 1941.
[11]^ "Product Digest: Reviews "Stormy Weather"," Motion Picture Herald, p. 103, May 29, 1943.
[12]^ J. E. Helmreich, "Gathering Rare Ores: The Diplomacy of Uranium Acquisition, 1943-1954." Princeton University Press, 2016.
[13]^ L. M. Libby, "The Uranium People," First Edition. New York: Crane, Russak, 1979.
[14]^ B. Foster, "TV Screenings," The Times, San Mateo, p. 45, Dec. 13, 1961.
[15]^ J. B. (James. B. Schriever, "Complete Self-Instructing Library of Practical Photography." American School of Art and Photography, 1909.
[16]^ "Kodak Reference Handbook." Eastman Kodak Company, 1946.
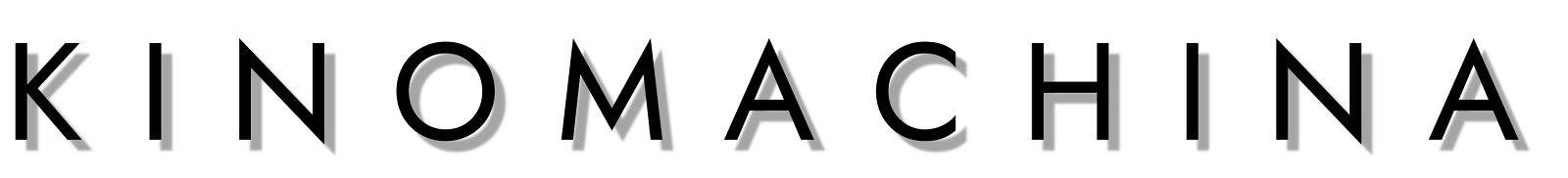

0 Comments
Post a Comment